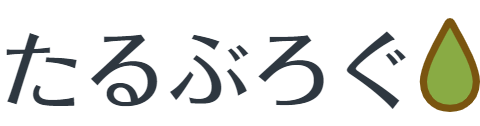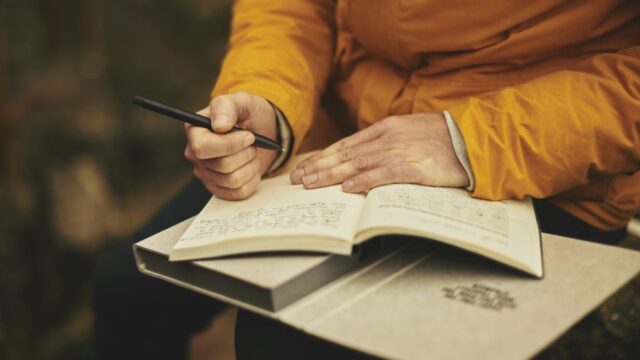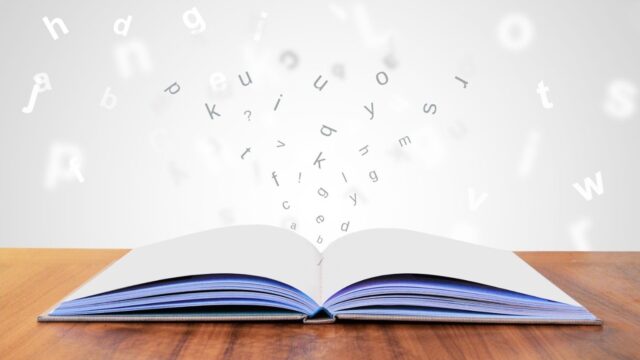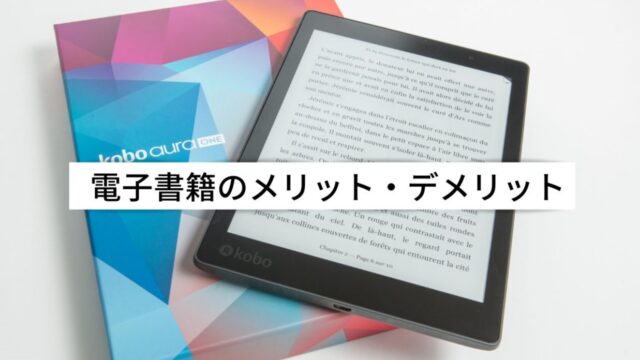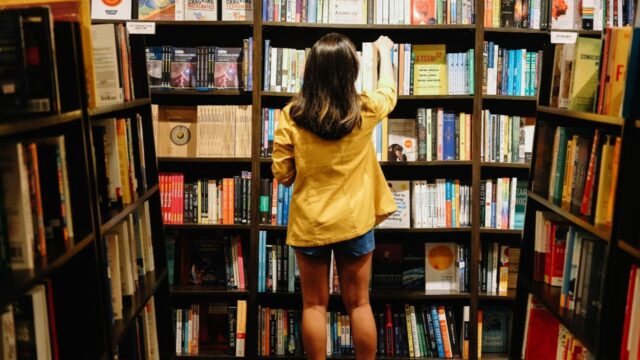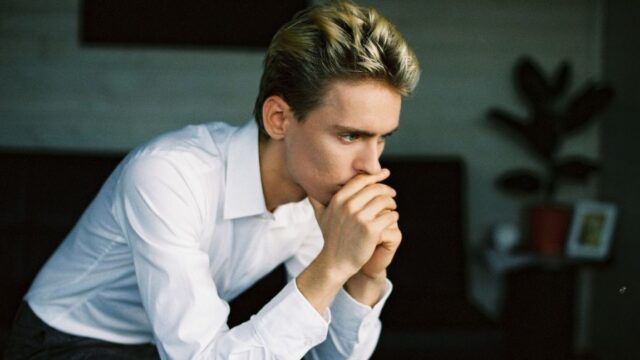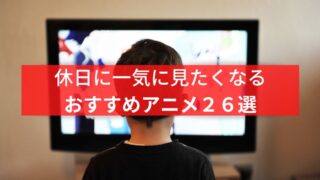勉強の効率を上げられる、休憩の取り方を知りたい。
そのような方へ、本記事では実際に僕がに使って効果があると感じた、おすすめの休憩法7つを紹介します。
効果的な休憩の取り方を知って、勉強の効率を上げたい方はぜひご覧ください。
勉強の効率を上げるおすすめの休憩法7選
① 音楽を聞く

1つ目は、休憩中に音楽を聞くことです。
音楽を聞くことには次のメリットがあります。
音楽を聞くことで、ドーパミンというモチベーションを上げる脳内物質が出るため、やる気がアップする。
そのため休憩中に音楽を聞くことで、モチベーションが上がり、勉強に集中できるようになるのです。
ここで大切なのは、音楽を聞くタイミングです。
中には、音楽を聞きながら勉強をしてる人もいると思います。
音楽を聞きながら勉強するとやる気が出てくる。
しかし、音楽を聞きながら勉強することは逆効果であることが分かっています。
この理由は、私達は2つのことを同時にできないことにあります。
そのため、音楽を聞きながら勉強すると両方に意識が向き、勉強の効率が下がってしまうのです。
つまり、音楽を聞きながら勉強すると、ドーパミンによりやる気が出るため、音楽を聞いたほうがはかどると感じますが、実際には2つのことを同時に行っているので効率は下がっているのです。
実際には音楽を聞かないで勉強した方が、勉強の効率は上がるよ。
そのため効果的な音楽の使い方は、勉強の前に音楽を聞いてやる気をアップさせ、勉強中は聞かないようにすることです。
音楽のメリット
⭕ 音楽を聞くことでドーパミンが出て、やる気がアップする
音楽のデメリット
❌ 勉強しながら音楽を聞くと、勉強の効率が下がってしまう
→ 勉強の前に音楽を聞いてやる気を上げ、勉強中は聞かないようにするのがおすすめ
このように勉強中は音楽を止めて、休憩中にだけ音楽を聞くことで、勉強の効率を上げていきましょう。
② 運動をする

2つ目は、休憩中に運動をすることです。
運動には次のメリットがあります。
・やる気をアップさせる、ドーパミンという脳内物質が出る
・脳を刺激することで脳が活性化する
・血流の流れが良くなり、血液中の酸素や栄養を脳に届けてくれる
これらのメリットから休憩中に運動をすることで、勉強の効率を上げることができます。
運動は、勉強の前後と勉強をしながらの両方で行うことで効果を発揮します。
1.勉強の前後に運動する
勉強の前後に運動することで、勉強の効率を上げることができます。
勉強の前後に運動には、次のような効果があることが科学的に分かっています。
勉強の前に運動
ウエスト・ロンドン大学が明らかにした事実で、
10分だけエアロバイクをこいだ被験者は、その直後から脳のパフォーマンスが改善されました。
物事を分析する能力が、運動前より 14%も向上しています。
勉強の後に運動
2017年に、ニュー・サウス・ウェールズ大学がこんな実験をしています。
被験者は 20代の男女。
全員に見知らぬ人物の顔写真を覚えさせた後、半分のグループにのみ歩行運動器具で 5分ほど歩くよう指示しました。
その効果は明らかで、しばらく後に記憶テストを行ったところ、運動をしたグループは男性の成績が 10%ほどアップしました。
女性にいたっては 50%近くも記憶力が改善していたのです。
『引用元:最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法|メンタリストDaiGo』
これらをまとめると、勉強の前後の運動には次のメリットがあります。
勉強前の運動
物事を分析する能力が14%上がる
勉強後の運動
男性:記憶力のテストで10%上がる
女性:記憶力のテストで50%近く上がる
そのため、休憩中に運動をして勉強の効率を上げることがおすすめです。
僕のおすすめは、スクワット・階段の上り下り・散歩
などを行うことです。
勉強の前後にこれらの運動をすることで、勉強の効率を上げていきましょう。
2.勉強しながら運動する
勉強の前後に加えて、勉強中に運動することでも効率を上げれることが分かっています。
例えば、メンタリストのDaiGoさんは作業の効率を上げるために、ステッパーをこぎながら仕事を行っているそうです。
しかし、勉強しながら運動することはなかなか難しいと思います。
そこで僕が勧めるのがスタンディングデスクを使うことです。
立ちながら学習することでパフォーマンスを上げれることが、研究により分かっています。
テキサス A& M大学の実験によれば、
スタンディング・デスクで授業を受けた小学生は作業の達成度が 12%上がり、子ども同士の私語が減ったうえに、グループディスカッションへの積極性も改善しました。
12%の達成度アップは、集中力が 1時間あたり7分ほど伸びた計算になります。
さらに長期の研究では、スタンディング・デスクで頭が良くなったとの報告も出ています。
こちらは高校生を対象にした実験で、24週間、立ったまま勉強を続けさせたところ、大半の生徒は認知テストの成績が上がり、脳の実行機能にも改善が見られました。
『引用元:最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法|メンタリストDaiGo』
また、日本人は座る時間が世界で1番長く、座る時間が長いほど様々なデメリットがあることが分かっています。
シドニー大学の研究によると、
1日に座っている時間が 4時間未満の人と比べ、11時間以上の人は、40%も死亡リスクが高まりました。
同研究者によるとテレビをじっと座って見続けると、 1時間ごとに平均余命が22分間短くなると推定されるとのこと。
アメリカ UCLAの研究では、
座っている時間が長い人ほど、内側側頭葉が薄くなることが報告されました。
内側側頭葉が薄くなると、認知機能が低下し、アルツハイマー病など認知症の発症にもかかわります。
座り続けることは、脳にも身体にも極めて悪影響を及ぼします。
『引用元:学び効率が最大化するインプット大全|樺沢紫苑』
そのため、スタンディングデスクで座る時間を短くすることで、これらのリスクを減らすことができるのです。
まとめると、スタンディングデスクには次のメリットがあります。
・作業の達成度が12%上がり、集中力が伸びる
・認知テストの成績が上がり、脳の実行機能が改善する
・死亡リスクを下げられる
・アルツハイマー病などの認知症のリスクを下げられる
スタンディングデスクには集中力を上げるだけでなく、健康面でも効果があります。
しかし、中にはスタンディングデスクは効果がないという意見や、立ちっぱなしは腰を痛める原因になるという意見もあります。
メリットとデメリットを比べて、自分自身で考えて選ぶようにしましょう。
興味のある方は、僕の使っているスタンディングデスクを紹介します。
僕はスタンディングデスクを使ってから、前よりも長い時間集中して作業できるようになったと感じてます。
僕が購入したのは、メンタリストのDaiGoさんが勧めていたスタンディングデスクです。
スタンディングデスクは、僕が買ってよかったと思うものの1つなので、気になる方はぜひ使ってみてください。
また他にも買ってよかったものをランキングでまとめたので、興味がある方はどうぞ。

③ 目を閉じる

3つ目は、休憩中に目を閉じることです。
休憩中にスマホで、SNSやYoutubeを見ているという人は多いと思います。
休憩中はスマホを見ているよ…
しかしこれではしっかりと休むことができず、むしろ逆効果になります。
脳を休ませたいのに、スマホから情報を入れてしまったら脳は休むことはできないのです。
そこでおすすめなのが休憩中に目を閉じて、情報を遮断することです。
休憩中に目を閉じることには、次の2つのメリットがあります。
1.視覚から入る情報を遮断して、脳を休められる
2.覚えたことが記憶に定着しやすくなる
私たちは、視覚から約9割の情報を得ていると言われています。
そのため、目を閉じて視覚からの情報が入ってこないようにすることで、脳を休ませることができるのです。
スマホを見ると、視覚から情報が入ってくるので、脳を休ませることができません。
また目を閉じて脳を休ませることで、記憶を定着させることができます。
よく『寝てる間に記憶は定着するから睡眠は大切』と言われるように、脳は休んでいる時に覚えたことを記憶に定着させるのです。
そのため覚えたことを記憶に定着させたい方は、休憩中に目を閉じるようにしましょう。
休憩中にアイマスクを付けるのもおすすめです。
休憩中にスマホを触ってしまう人は、休憩前に離れた場所にスマホを置くようにしましょう。
スマホが近くにあるとつい使ってしまいます。
そのためスマホを遠くに置いて、触ることを面倒にすることで、スマホに触りにくくなるのです。
休憩中についスマホを使うことが多い人は、目を閉じることを試してみてください。

④ 休憩時間を測る

4つ目は、休憩する時間を決めて休むことです。
少しの時間休もうとして、気づいたら結構な時間休んでしまったという経験をした方は多いと思います。
ちょっと休憩しようと思ったら、気づいたら何十分もたっていた。
そのような方におすすめなのが、タイマーを設定して休憩する時間を決めてから休むことです。
このように時間を決めて休む方法に、ポモドーロ・テクニックというものがあります。
25分作業したら、5分休憩することを1セットとして、4セットごとに30分間の休憩を取る方法。
1⃣25分、5分 → 2⃣25分、5分 → 3⃣25分、5分 → 4⃣25分、5分 → 30分休憩
この方法のメリットは、休憩時間だけでなく作業時間も決めることで、やる気が出ることです。
時間を決めずに作業するよりも、制限時間を決めた方が集中力はアップします。
25分だけ集中して作業するぞ!
このテクニックでは作業の時間を25分としていますが、集中力は人によって違うので自分にあった時間で設定するようにしましょう。
ちなみに僕は50分作業したら、10分休むようにしています。
また休憩時間は長く取りすぎるとやる気がなくなってしまうので、5~10分に設定することをおすすめします。
作業と休憩のメリハリをつけたい方は、ぜひこの方法を試してみてください。
⑤ 瞑想をする

5つ目は、休憩中に瞑想をすることです。
先程の説明でもありましたが、脳は休んでいる時に記憶を定着させます。
そのため瞑想を行い、他のことを考えないようにすることで、記憶の定着を助けてくれるのです。
また、瞑想には集中力を上げる効果があること分かっています。
ウィスコンシン大学による類似の研究では、
1回10分のマインドフルネス瞑想でも集中力が上がり、認知テストの成績もアップしたと報告されています。
『引用元:最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法|メンタリストDaiGo』
集中力の向上だけでなく、瞑想には次のメリットもあります。
・ストレスの減少
・意志力の向上
・感情をコントロールしやすくなる
僕も瞑想を習慣にしてから、集中力と意志力が上がったと感じています。
瞑想する時のポイントは次の2点です。
・呼吸に意識を向けて集中する
・他のことが思い浮かんだら呼吸に意識を戻す
瞑想にはいろいろなやり方があるので、詳しく知りたい方はネットやYoutubeで調べてみましょう。
ちなみに瞑想が正しくできてるか確認したい方には、オーラリングがおすすめなので、興味がある方はどうぞ。

⑥ 換気をする

6つ目は、休憩中に換気をすることです。
換気の悪い部屋よりも、換気の良い部屋の方がパフォーマンスは高くなることが分かっています。
そのため、休憩中に換気をして空気を入れ替えることで、パフォーマンスを上げることができるのです。
換気の目的は、空気を入れ替えて二酸化炭素の濃度を減らすことです。
私達は酸素を吸って、二酸化炭素を排出しています。
そのため換気のしない部屋にいると、二酸化炭素の濃度が増えしまいます。
そのため、換気をしないと二酸化炭素の濃度が増えるので、パフォーマンスが下がるのです。
部屋に1人だけなら影響は少ないかもしれないけど、換気は簡単にできるので試してみるのをおすすめします。
換気をする時は次の2つ点を意識しましょう。
・換気の時間は、1時間に5~10分間行う
・対角線上の窓をあけて、空気の通り道を作る
集中力を上げたい方は、休憩中に換気を行うことを試してみてください。
⑦ 水分補給をする

7つ目は、休憩中に水分補給をすることです。
水分補給をすることで、作業への集中力を上げることができます。
私達の体は、約60%が水分でできていると言われています。
そのため水分補給が大切になるのです。
水分不足の状態だと、集中力は下がってしまいます。
喉が乾いている状態だと、集中できなくなると思います。
そこで大切なのが、こまめな水分補給をすることです。
できれば、作業をしながらこまめに水分を取ることがおすすめです。
それが難しい方は、少なくても休憩中には水分を取るように意識しましょう。
まとめ
本記事では、勉強の効率を上げるおすすめの休憩法を紹介しました。
休憩中に紹介した方法を使うことで、勉強の効率をぜひ上げてみてください。
また、効果的な休憩や勉強の方法について詳しく知りたい方は、こちらの本がおすすめです。
興味がある方は読んでみてください。